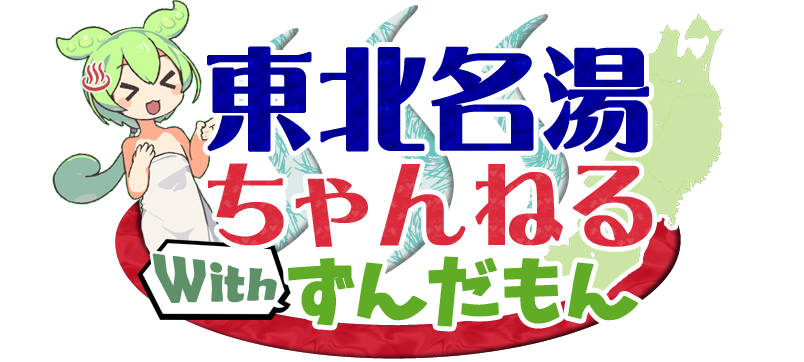| 番号 | |
|---|---|
| 県市 | |
| 基本情報 |
|
| 成分表1 |
|
| 成分表2 |
|
| 成分表3 |
|
| 成分表4 |
|
| 成分表5 |
|
| 総評 |
|

ヌルヌル値ランキング
こちらの研究結果(皮膚のヌルヌル感に及ぼす温泉水の特性)のヌルヌルするかを求める数式を元に、独自にメタケイ酸、メタホウ酸、水酸化物イオンに電離補正と温度補正を加えて導き出した数値がプラスの場合、ヌルヌルする温泉水となり、この+の数値が大きいほど、強いヌルヌルを感じる泉質となります。
なお、ヌルヌルしない(マイナス)になった場合はマイナスの数値に関わらず、ヌルヌルしないという結果のみを表わすことになりますが、本表ではマイナスになった施設(ヌルヌルしない)は掲載しません。
但し、実際に入浴してヌルヌルを感じた場合は特別に記載します。
本ランキングは上記研究結果を元に、当方独自の計算方法で導き出した数値です。
素人が作成したものですので信憑性を証明することは出来ないものです。
それらを踏まえた上でご活用ください。
成分分析表を調査し、ヌルヌル値がプラスであった場合、随時追記します。
実際の計算方法や、ヌルヌル値の求め方などはページ下部に記載しています
自身でヌルヌル値を計算してみた方は計算表(Excel)をダウンロード出来ます
また、『BIZ UDPゴシック』が必要となります。フリーフォントですので合わせてDLしてください
バージョン切り替え準備中
ヌルヌル数値ランキング【Ver:5.00】
新しいVerの切り替えしました(2025/10/15)
5.00以降は根本的な基準値・計算方法が変更され、ヌルヌル値の範囲が狭まりました。
(おおよそ0~10くらいの範囲となります)
↓このボタンから切り替えてご覧ください(読込にやや時間がかかります)↓
表の見方
ヌルヌル値が実際のヌルヌル度となります。
0以上でヌルヌルを感じますが、配合や天候などで0未満でもヌル感がある場合もあります。
特にモール泉はヌルトロを感じる場合がありますが、成分表の数値では測定出来ません。
スマホ、PCどちらからも確認できますが、PCだと全ての項目が表示されるように調整しているのでPCからの確認がオススメです。スマホの場合は左右スライドに対応しています。
補正有・体感モデルについて
こちらは以下の独自補正を加えています。
✓ 加水によるヌル感の稀釈
✓ 加温によるヌル感の上昇
✓ 特定のpHを超えている場合のメタけい酸・メタホウ酸の電離補正、水酸化物イオンの補正
✓ 溶存物質総量が一定以下(薄い)場合のヌル感の補正 など。
実際に入浴した際の体感に近い数値となっていますので、基本的にはこちらの「補正有・体感モデル」を参考にするのがオススメです。
詳細解説はページ下部に記載しています。
補正なし・化学モデルについて
こちらは独自要素を加えず、ページ冒頭の論文を元にした計算結果です。
例えば、高アルカリ・メタけい酸が非常に多い場合でも「メタけい酸水素イオン」が記入されていない場合は計算していないので、あくまで化学・数字ベースで見たい方はこちらを参考にしてください。
なお、あくまで体感モデルの方が実際の入浴感に適合している為、こちらでは評価は行いません。
ヌルヌル泉の一覧はこちら
「◯.◯X」のX部分はフォントや表示形式などの微調整となります。
- Ver 1.0:論文通りにヌルヌル値を測定 (化学的分析版)
- Ver 2.0:Ver 1.00の炭酸イオン(CO₃²⁻)をmolに変換する際、「換算当量 17.008」で計算していたものを「モル質量(60.009)」に変更。
Ver 1.00では、溶け込んだイオンが表記されていた場合のみ反映されていたが、表示されていない場合はメタケイ酸・メタホウ酸を電離補正計算を行って反映。 - Ver.3.0:「化学的分析モデル」ではなく、「体感的モデル」に変更。
それに伴い、炭酸イオンを「換算当量 17.008」に再度変更。
水酸化物イオンも未掲載の場合、自動的に電離補正を追加。
「加水」があった場合はヌルヌル総量が減るので、温度に合わせて自動的にマイナス補正し、逆に冷鉱泉の場合は加温した際にはヌルヌル感が増すので、プラス補正を追加。 - Ver.3.1:100℃近い高温泉の場合、自動マイナス補正率が強く出過ぎてしまったので、最低でも70%以上のAeを維持するように変更し、冷鉱泉を加温した際のヌルヌル感のプラス補正がやや強かった(20℃の源泉 → +26.4%上昇)ため、0.012→0.006に変更。
- Ver.4.0:溶存物質総量が少ない場合(1,600mg以下)は、他の阻害成分が少ない分、よりヌルヌル体感が強く出やすくなるため、最大補正1.2倍の段階的希薄補正用数式を導入。
- Ver4.1:成分表に「体感モデル値」と「化学モデル値」を導入。
- Ver.4.2:4.1まではヌルヌル値は-9.9999までは表示。-10以下の場合は「-10以下」と表示を行っていたが、そもそも0以下の場合、分母が0以下となり式が破綻し、正常な結果が得られない為、0以上を表示し、0未満は「ー」表記に統一。それに合わせてヌルヌル評価0-1間を「×:ヌルヌルしない」から「×:ほぼ感じない」に変更。
また、ランキング表に掲載していたマイナス表記は全て撤廃し、0表記に変更。実際にヌルヌルするが計算結果がマイナスになった場合は「0」にした上で、補足コメントに記入。 - Ver.5.0:一部源泉がVer.4.2で計算すると暴走したヌルヌル値を出力した為、原因を究明した結果、炭酸イオンの「換算当量 17.008」が原因と判明。体感モデルによる電離補正を含めた現状「モル質量(60.009)」で計算し直した結果、ランキング(体感的にも)も大きく差異が出なかった為、「モル質量(60.009)」で計算し直しました。
また、上記によるランキング数値も0.0001~約10程度になった為、評価枠も変更しました。
【以下は見えない部分による内部変更】
・加水有の場合は最大0.7→0.8に変更し、手動でも調整出来るように調整。
・炭酸水素イオンと炭酸イオンの比率に異常がある場合はエラーが出るように調整。
・イオンバランス、炭酸系イオン、アルカリ度を表記 等 - Ver.5.1:極端に陽イオンと陰イオンのバランスが崩壊している場合は「アラーム」を追加し、補正するように計算を追加。
※基本的に見える部分に変更はありません。
ランキング内の『評価』について
『◎・◯・△・✕』の4段階で評価し、実際に入浴した際に『ヌルヌル値に対する評価』を示します。
投稿主の主観に基づくものなので、時期や時間帯によって大きく異なる可能性があります。
評価は以下の通り。
◯:数値通りのヌルヌル感がある。
△:数値に比べるとヌルヌル感が不足しているが、ヌルヌル感は残っている。
✕:ヌルヌル感は大幅に失われている。元から1.0以下の温泉で実際に感じない。など。ほぼ皆無な場合。
◎:数値以上のヌルヌルを感じる。
―:成分表のみで算出し、実際に入浴していない(未調査)の施設。評価対象外。
ランキング上位の『◯』は『ランキング上位の数値に相違ないヌルヌル感』であり、◎と比べて劣っている表現ではなく、あくまで『ヌルヌル実数値に対しての評価』です。
また、この評価は『体感モデル』を基準としています。
例えば、『しんとろの湯』は『体感M:10.38833』『化学M:4.38850』となっていますが、体感モデルの数値に対しての評価となります。
♨ 温泉の「ヌルヌル感」は数値で測れる!
ヌルヌル感(滑感)は、主にアルカリ性イオンの種類・濃度・pH・硬度(Ca+Mg)が影響します。
体感モデルではこれらをmmol換算・電離率補正・温度補正・希薄補正して数値化します。
有効アルカリ成分(Ae)の構成要素
ヌルヌルするのに必要な成分です。バランスよく含まれていても、いずれかの成分が突出していても、ヌルヌル感は発生します。 また、有効アルカリ成分とありますが、この成分が含まれていれば『中性』でもヌルヌルする温泉はあります。
| イオン | 役割 | 補正係数 |
|---|---|---|
| OH⁻(水酸化物) | 強アルカリの主因 | 1 |
| HS⁻(硫化水素) | ヌル感に寄与 | 1 |
| CO₃²⁻(炭酸) | とろみ感 | 1 |
| HSiO₃⁻(メタケイ酸水素) | 弱酸性由来のヌル感 | 1 |
| BO₂⁻(メタホウ酸) | 弱めのヌル感 | 0.18 |
| HCO₃⁻(炭酸水素) | 中和作用 | 0.10 |
Ae(有効アルカリ成分)計算式
Ae = 1.0 × [NaOH系(CO₃²⁻)] + 0.18 × [NaBO₂系(BO₂⁻)] + 0.10 × [NaHCO₃系(HCO₃⁻)]
Ae = OH⁻ + HS⁻ + CO₃²⁻ + HSiO₃⁻ + 0.18 × BO₂⁻ + 0.10 × HCO₃⁻
メタけい酸・メタホウ酸の電離補正(イオン未掲載時)
メタ〇〇酸は「そのまま」ではヌルヌルの要因にならないので、補正を行います。
とりあえず『メタ〇〇酸』と『メタ〇〇(水素)イオン』は全く別物と考えてください。
メタけい酸の電離率(HSiO₃⁻生成)
- 目安:pH9.6で約50%がHSiO₃⁻に変化
- pHが高いほど電離率↑により、ヌルヌル感↑
=MAX(0, (メタけい酸[mg] ÷ 78.10) × (1 ÷ (1 + 10^(9.6 - pH))))
メタホウ酸の電離(BO₂⁻生成)
メタホウ酸(HBO₂)も、pHが高いと電離してBO₂⁻になります。
HSiO₃⁻ほど強いヌルヌル感は生みませんが、補助的にヌル感を強める効果があります(換算係数は0.18)。
=MAX(0, (メタホウ酸[mg] ÷ 61.83) × (1 ÷ (1 + 10^(9.2 - pH))))
何故、このような電離補正を行うのか?
よく「メタけい酸がヌルヌルに起因している」と言われますが、それは誤りです。
正しくは、温泉に溶け込んだ(イオン化)メタけい酸――メタけい酸水素イオンが影響します。
pHが高い場合のみ、水中でイオン化(=電離)してHSiO₃⁻になります。
このHSiO₃⁻こそが、皮膚と化学反応し「とろみ・ヌル感」を生み出す主成分なのです。
しかし、殆どの成分表にはイオン化された数値(メタけい酸水素イオン・メタホウ酸イオン)の項目自体がありません。
pHが高い場合はイオン化して一定数存在するとされるため、独自に電離率を計算して判定に加えています。
非電離(メタけい酸・メタホウ酸)の成分がどれだけ豊富でも、pHが低ければ電離せず=ヌルヌルしない。
逆に、少量でもpHが高く、電離率が高ければヌルヌル感が強まります。
また、同じ理由でヌルヌル値の判定に利用される『OH⁻(水酸化物)』も、pHが上昇するにつれて電離化が進み、少なからず発生します。OH⁻(水酸化物)もpHに合わせて自動的に補正しています。
『メタけい酸水素イオン』の補足
メタけい酸水素イオン(Hydrogen metasilicate ion)
化学式:HSiO₃⁻ 電荷:1-
特徴:中性または弱酸性条件で見られることがあり、中間的な段階のイオン。けい酸の電離段階で生成されます。
→ 中性以下で発見されるのに高アルカリで増えるのは何故か?
HSiO₃⁻ というイオン自体は、中性環境ではそれなりに安定して存在できるため、「見られる」ことはあります。
しかし、中性pHで新たに電離が進むことはありません。電離が進む(発生)するのは高アルカリ時のみです。
なので、高アルカリ源泉・メタけい酸が多量に含まれたヌル泉が浴槽に注がれ、鮮度が劣化して中性寄りにpHが上昇したとしても、イオン化したヌルヌル成分はそのまま存在できることから、ヌルヌル感は大きく減少しないと考えられます。
温度・加水補正(42℃基準)
温泉のヌルヌル感(粘性)は、成分量だけでなく源泉温度や加水・加温の有無によっても大きく変化します。
このため、分析値から算出されるヌルヌル指数(Ae値)には、源泉の状況に応じた補正を加えています。
42℃を基準温度とし、低温(加温あり)では体感上の増加補正、高温(加水あり)では稀釈による減少補正を行います。
なお、実際の温泉では常に加水を行うことは稀なため、極端な減少を防ぐために、どんなに高温でもAeは80%(0.8倍)以上を維持するように設定しています。
| 条件 | 補正式 | 説明 |
|---|---|---|
| 加水あり(自動補正) | Ae × MAX(0.8, 1 - 0.006 × (MAX(源泉温度,42) - 42)) |
42℃を超えると、1℃ごとに0.6%ずつAeを減少。高温でも最低80%保持。 |
| 加温あり | Ae × (1 + 0.006 × (42 - 源泉温度)) |
42℃未満の冷泉を加温した場合、1℃ごとに+0.6%補正(加水がない場合のみ有効)。 |
| 両方なし | Ae |
補正なし。分析値そのまま。 |
| 加水+加温あり | Ae × 加水補正(上記) |
加水補正を優先。加温ブーストは無効。 |
加水と加温が同時に行われる場合は、加水による成分の希釈が支配的であるため、加温ブーストは適用されません。
これは、実際の温泉管理でも「高温源泉を加水して温度調整した場合」は、体感的なヌルヌル感が増さないことを再現しています。
以下は温度ごとの自動補正率の目安です:
| 源泉温度(℃) | 自動補正率 | 減少率 |
|---|---|---|
| 35 | 0.8 | -20% |
| 42 | 1.0 | ±0% |
| 50 | 0.952 | -4.8% |
| 60 | 0.892 | -10.8% |
| 70 | 0.832 | -16.8% |
| 80 | 0.8 | -20%(下限) |
| 100 | 0.8 | -20%(下限) |
加温すると何故ヌルヌル感が増す?
冷たい温泉(冷鉱泉)は、そのままだと成分が電離しにくいため、ヌルヌル感が弱い傾向にあります。
- 加温すると、水中での電離(イオン化)反応が促進されます
- 特に「メタけい酸(H₂SiO₃)→ HSiO₃⁻」や「H₂O ⇆ H⁺ + OH⁻」のバランスが変化
- その結果、ヌル感の元となる陰イオン(HSiO₃⁻, OH⁻, CO₃²⁻ など)が増加
また、加温は基本的に成分に影響を与えないとされています。
但し、ガス成分やラドンは抜けるので、二酸化炭素泉や硫化水素型の硫黄泉、放射能泉は少なからず影響が発生します。
希薄補正(Ver.4.0以降)
温泉成分は、源泉によって大きく濃度が異なります。
一般的に、溶存成分量が少ない源泉では、わずかな成分でも実際には特徴(ヌルヌル感)として体感されることがあります。
そこで、体感モデルでは「溶存物質量(mg/kg)」が少ない源泉ほどヌルヌル感を割り増す『希薄補正』を導入しています。
補正式
希薄補正係数 = MIN(1.2, 1600 ÷ 溶存物質量 ) Ae’ = Ae × 希薄補正係数
- 基準値 = 1600 mg/kg
- 最大補正 = 1.2倍(極端な源泉を過大評価しないための上限)
当初は単純温泉の基準値である1,000mg未満で計算を行いましたが、実体感とズレが発生した為、調整を経て実体感と差が少なかった1,600mgを基準値にしました。
つまり、成分量が基準を下回る「極めて薄い温泉」は、ヌルヌル感が実際より強く算出されるように自動で調整されます。
逆に、基準を十分に超える温泉では 1.0(補正なし)の係数となります。
Ae_c(硬度による補正)
カルシウム(Ca²⁺)と、マグネシウム(Mg²⁺)が多いと、その分、ヌルヌル感は失われます。(ヌルヌル感阻害成分) 非常に高アルカリ、豊富なメタけい酸(正しくはメタけい酸水素イオン)が含まれているにもかかわらず、ヌルヌルしない場合は殆どがカルシウムが多い場合となります。
Ca²⁺+Mg²⁺のmmol値に基づいて以下を使用:
硬度比 = Ca+Mg ÷ (Ca+Mg + Ae) Ae_c = 0.3 × (1 - 硬度比) ÷ (0.55 - 1.55 × 硬度比)
ヌルヌル指数 = Ae ÷ Ae_c × 希薄補正係数
この導き出された数値がランキングの数値となります。
※化学モデルの場合は希薄補正係数は1倍固定
ヌルヌル値 評価基準
Ver.5.0以降の基準値です。 ※Ver.5.0以降は成分表右下にVerが記載されています。| ヌルヌル指数 | 判定 | 肌触り | 0未満 | ✖:感じない | ヌルトロ感はなし |
|---|---|---|
| 0.00001 ~ 2 | △:ややトロトロ | わずかにトロみを感じる |
| 2 ~ 4 | ◯:トロトロ | 明確なトロみを感じる |
| 4 ~ 6 | ◎:ヌルヌル | 強いヌル感、まとわりつく湯ざわり |
| 6 ~ 8 | ★:超ヌルヌル | 濃厚なヌル感、肌を包み込む質感 |
| 8 以上 | ☆:奇跡のヌルヌル | 全国でも稀少なヌルヌル泉 |
| 〜 1.0 | ✖:ほぼ感じない | ややヌル感があるかも? |
| 1.0 ~ 2.5 | △:ややヌルヌル | とろみを感じ始める |
| 2.5 ~ 4.0 | ◯:しっかりヌルヌル | 明確にヌルヌルを感じる |
| 4.0 ~ 7.0 | ◎:強いヌルヌル | まとわりつく感 |
| 7.0 ~ 12.0 | ★:超ヌルヌル | 濃厚なヌル湯 |
| 12.0 以上 | ☆:奇跡のヌルヌル | 世界的にも稀少なヌル泉 |
ランキング値の「0.0000」について
何かしらが原因で『実際はヌル感があるのにヌル値がマイナス』になってしまった源泉、または解説用です。
補足コメントに記載していますので、そちらを確認してください。
何故、マイナスの結果(正しくない測定)となるのか。
一番大きな原因は参照している『成分分析表が異なる』ことです。
成分表は10年に1度の更新と測定間に長い年月が指定されており、その間に成分が変わってしまうことが多いです。
また、前日が大雨だった。山間部で雪解け水が混じっている時期に測定など、通常時とは異なる条件で測定した成分表の可能性もあります。
混合泉の場合は基本的に同じような泉質のものを混ぜますが、中には全く異なる泉質を持つものを合わせていることがあり、その場合は混合比率によって変化します。
このように成分分析表は様々な条件下で複数回採取して測定し、基準値を求める。というものではないので、かなりアバウトなものとなっているので、比較的最近の分析だったとしても異なることが多々あります。
このランキングはあくまで成分表の数字を基準にしているので、それに差異があると当然ズレるのが要因です。
(勿論、独自の計算方法なので計算や参照自体が誤っている可能性もあります)
まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 必要データ | pH、各成分mg値、pH、溶存物質総量、源泉温度、加水・加温状況 |
| 電離補正 | メタケイ酸・メタホウ酸・水酸化物イオンを未記入であった場合のみ、pHによって自動変換 |
| 温度補正 | 加温・加水の有無により動的補正 |
| 希薄補正 | 源泉の濃さ(溶存物質)により動的補正 |
| 評価結果 | ヌルヌル指数とラベル(✖〜☆)を出力 |
注意事項
- 本ランキング・数値は当ちゃんねる(ブログ)独自の集計によるもので、必ずしも正しいものではありません。
- あくまで成分分析表を元に、科学的に検証した内容であるため、成分分析表が古いものであったり、気象条件が悪い中で計測したもの。豪雪地帯で雪解け水が混じるような時期に計測したものなど、様々な条件下によって実際の成分量とは大きく異なる場合があります。
- 本計算は研究結果の時点で約94%当てはまったが、逆に言えば6%当てはまらない場合もあります。(Vor:1.00) 現在利用されているVol:2.00以降のモデルは当ちゃんねる独自の計算要素を入れているので、完全にオリジナルとなりますので、利用・参考の際は予めご理解ください。
- 本データを引用・参考利用する場合は『東北名湯ちゃんねる(引用元:https://onsen-ch.com)』または『東北名湯ちゃんねる (https://www.youtube.com/@onsen-ch)』と引用元を必ず表記してください。(事前・事後連絡は任意)
特定企業などが利用する場合でどうしても引用元・参考元を表示したくない(出来ない)場合は、利用前に必ずお問い合わせの上で、許諾を得てから利用してください。 - 本データは参考用であり、当ちゃんねる(ブログ)・管理人はデータの正確性に関して一切の責任を負いません。
情報提供について
本表をより充実させる為、ヌルヌルしている温泉の『成分分析表』を随時募集しています。
お問い合わせフォーム、または『info@onsen-ch.com』に、『数値がはっきり見える成分分析表』と『成分に影響を与える項目(加水などの有無)』の写真をお送りください。
写真は可能な限り、リサイズせず、オリジナルサイズのままお送りください。